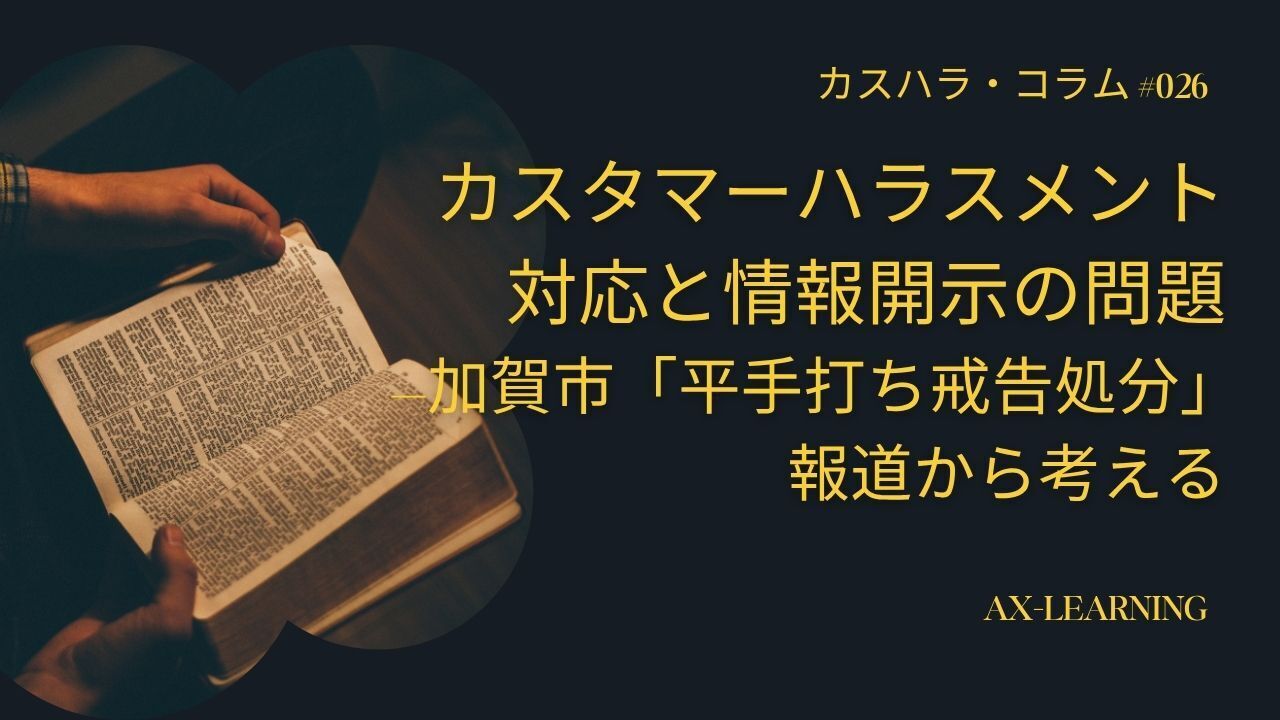
カスタマーハラスメント対応と情報開示の問題—加賀市「平手打ち戒告処分」報道から考える
2025年06月13日 12:22
2024年1月16日、石川県加賀市役所に来庁した男性が市の男性職員につばを吐きかけ、それに対して職員が反射的に平手打ちをした。そして、加賀市役所は、この職員に対し3月31日付で戒告処分を下したと6月12日に発表した。市は、被害を受けた来庁者に10万円の和解金を支払っている。ニュースソースは、北國新聞が6月13日5:01に配信した内容である。見出しは「加賀市が戒告処分 来庁者平手打ち職員」。記事では「来庁者が唾を吐いた」が、「カスタマーハラスメントを受けた事実は確認できなかった」と記述されている。
この一件は、カスタマーハラスメントと公務員対応、そしてメディアの報道の在り方に関して、多くの論点を投げかけていると筆者は考えるので、コラムにまとめます。
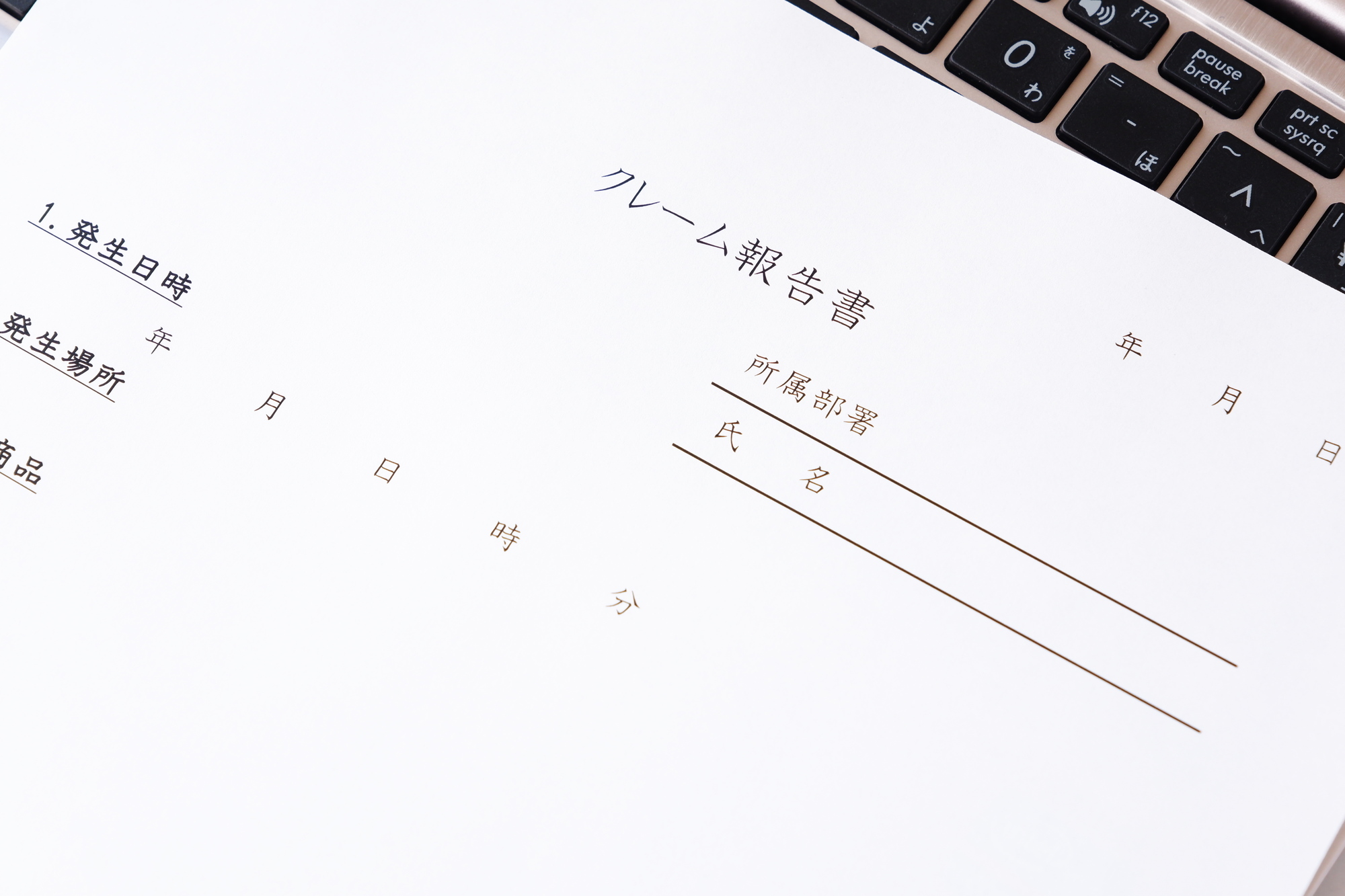
目次
1.「唾を吐きかけた」背景はなぜ報道されなかったのか?
2.カスハラはどこから始まるのか?
3.職員・社員が「唾を吐きかけられたとき」の適切な対応とは?
4.「反射的な平手打ち」は、責められるべき行為なのか?
5.まとめ
1.「唾を吐きかけた」背景はなぜ報道されなかったのか?
まず問題提起すべきは、新聞記事の情報量の少なさである。「唾を吐きかけた」という行為自体は、感情的な衝突の最終局面であって、そこに至るまでに何があったのかが最も重要である。行政窓口でのトラブルは、その多くが市民と職員の間の認識ギャップや不十分な説明と理解力の欠如であったり、市民の無理難題や暴力暴言などの行き過ぎた行為である。今回のケースは「唾を吐きかける」ほどのことがあったのだろうか?
報道では、その理由や前後の会話、やりとりの詳細が一切書かれていない。こうした状況説明を欠いたまま、「職員が処分された」という事実のみを伝えると、職員の説明や理解力、やる気の無さに不満が溜まった来庁者の怒りがピークに達してこの様になったのかと想像してしまう。もしこうだったとすれば、プロセスにはカスタマーハラスメントは無かったとなるが、市サイドにカスタマーハラスメントを誘発する要因があったと筆者は考えることになる。
今、カスタマーハラスメントの話題は社会の関心事項の一つだ。ゆえに報道機関としての責務は、単に事件の結果を報じることではなく、「なぜそうした行為が起きたのか」「当事者の言い分はどうだったのか」と、読者に多角的な視点を提供することではないか?そうしなければ、カスハラ問題と市民の暴行の関係性が見えず、何となくカスハラって怖いというイメージだけを残すことになってしまう。少なくとも、現段階の記事を読めば、「唾を吐きかけられるような態様で職員が対応をしていながら、反射的に手まで出した」「市は、来庁者が怒った原因(市サイドの瑕疵)を公表したくない」という憶測を残してしまう。
2.カスハラはどこから始まるのか?
そもそも唾を吐きかける行為自体が「暴行罪」に該当する可能性がある。刑法208条における暴行罪は、「人に対して不法に有形力を行使すること」で成立し、唾を吐くという行為もその中に含まれるとされている。
このため、「唾を吐きかけられる」被害に遭った職員は、その場で対応終了させる、それでも居直るのであれば警察への通報や被害届提出という選択肢も本来あったはずである。反射的に手が出たという点には一定の同情の余地はあるが、公務に従事する職員としては、まず冷静な記録と報告が求められる。ところが、恐らく加賀市ではこのような市民トラブルへの対応策が行き届いていなかったのだろう。もしくは、「しているつもりの研修」で効果が無かったのかもしれないが、これはどの組織でも起こっていることである。
そして、一番重要なことは、「職員に対して唾を吐きかけるという行為」までエスカレートさせてはいけないという事なのである。この観点で筆者の感覚では、職員も来庁者も不幸になっていると思われる。カスハラの定義や認定は、その自治体や企業ごとに規定を設けない限り、曖昧さが出てしまうものなので、だからこそ「カスタマーハラスメント対応方針・マニュアル」等の制定が必要なのである。今回のケースはカスハラではなかったと市が発表しているので、「唾を吐きかけられる」までに暴力性や執拗さ等のカスハラ該当用件は無かったと推測されるが、その間に来庁者が職員の高圧的な対応に怒りを覚えたのかもしれない。あるいは説明不足により来庁者の感情が高ぶった可能性もある。であれば、日ごろから窓口のサービスレベルに問題があるにもかかわらずそれに気づいていない市に問題があろう。逆に、職員が丁寧に対応していたにもかかわらず、来庁者の理不尽な要求がエスカレートしていった可能性も考えられる。この場合、他の職員や上長は何故フォローしたり複数対応をしなかったのか?やはり窓口トラブルの基本対応についての心得やルールを知っていない可能性が濃厚である。
つまり、唾を吐くという行為が「最後の一線」であるとしても、それに至るまで誘発する行為やその兆候があったかどうかを検証しなければならない。今回の件では、「カスハラは確認できなかった」とされているが、その過程の検証こそカスタマーハラスメント対応のケーススタディとして非常に重要なポイントと指摘しておきたい。
3.職員・社員が「唾を吐きかけられたとき」の適切な対応とは?
では、実際に唾を吐きかけられるという異常事態に直面した場合、自治体職員はどう行動すべきなのか。
① 相手が攻撃的・暴力的になってきたとき
まず初めに、カスタマーハラスメントの予兆対応としては「安全の確保」がリスクマネジメントの鉄則である。これには二点あり、ひとつは今回のように暴行事件に発展させない様に応対者が変わったり複数で対応するということと、二つ目は攻撃してくる対手と戦うのではなく逃げる方法の確認である。
② 唾を吐きかけられたその後
他の職員に応援に来てもらい複数対応をすることが原則と心得たい。そして、そこに至った経緯をまず第三者となる職員が確認し、応対した職員と来庁者双方の言い分を聞く。そのうえで、職員の非が強いようであれば謝罪対応が考えられ、来庁者に責めがあるようであれば「本日の対応を終了する」ことを告げ、今後の対応については後日協議の上、連絡する様に連絡先を確認し退庁を求める。※退庁に応じない場合の方法はまた別の記事に改めて記載する
③ 事実の即時記録
被害を受けたこと、その一連の内容を詳細に記録する。可能であれば第三者の目撃者に証言を求め、監視カメラ映像がある場合はその保存を要請する。
④ 上司・管理職への即時報告
感情的な反応よりもまずは組織対応。職場の上司や危機管理部署に即時報告する。
⑤ 医療機関での検査
唾液は感染症リスクを伴う場合もあるため、上長は、念のため医療機関の受診も検討すべきである。身体的リスクへの従業員フォローがカスハラ対応では重要視される。
⑥ 警察や弁護士への相談
唾を吐く行為は暴行に該当する可能性が高く、民事や刑事の対応を取るべき事例である。職員個人の判断ではなく、組織としての対応フローを整えておくべきだ。そして、庁内での検討の上、「注意」「警告」「刑事事件化」等を即座に判断できるようなスケールの作成が望まれる。
4.「反射的な平手打ち」は、責められるべき行為なのか?
本件のような、反射的な行動であっても暴力行為は認められないという見解は、法的には正しい。しかし一方で、唾を吐きかけられるという行為自体が非常に強い侮辱・攻撃にあたることもまた事実だ。
人として、怒りが込み上げるのは当然であり、「暴力は絶対にダメ」という建前だけで処理することには限界がある。自治体や企業は、こうした緊急事態に対する訓練やマニュアルを整備し、「怒りをどう処理するか」「どうやってその場を収めるか」といった実践的なカスハラ対応策を職員に身につけさせる必要がある。
5.まとめ
この事件を通じて浮かび上がったのは、カスタマーハラスメント問題に対する社会的な理解の浅さと、メディア報道の不完全性である。新聞記事がカスハラといったキーワードを挙げておきながら、その背景や経緯に触れないまま、表面的な「職員が戒告された」という事実だけを伝える構成になっているため、カスタマーハラスメント問題の本質が浮かび上がらない。また、市民の権利保護と職員の職場環境保全は、両立させなければならない課題だ。どちらかを切り捨てるのではなく、問題の経緯を可視化し、適切な線引きを社会全体で議論していく必要がある。だからこそ、「なぜ唾を吐いたのか」「どんな会話があったのか」を丁寧に伝えることが、今後の報道姿勢として求められる。
カスタマーハラスメントが社会問題化する今、個別の事件に学び、冷静な視点と制度設計で対処していくことが急務である。感情的な応酬に終わらせず、「冷静な記録」「的確な報告」「組織的対応」を徹底する。それが、自治体職員を守る唯一の手段であり、同時に市民との信頼関係を維持するための道でもある。
【執筆者】
◆参考Webサイト◆
カスハラの事をもっと知りたい: https://www.ax-learning.jp/column/customer-harassment
カスハラ講演会を開きたい: https://www.ax-learning.jp/lecture/customer-harassment
厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/
あかるい職場応援団: https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
#カスタマーハラスメント対応策 #カスタマーハラスメント対応方針 #カスタマーハラスメント対策企業マニュアル #カスタマーハラスメント対応研修 #カスタマーハラスメント対策 #職場環境改善 #ハラスメント相談窓口 #従業員保護 #企業リスク管理 #クレーム対応 #クレーム対応研修 #苦情対応研修 #不当要求研修 #難クレーム対応研修 #異常クレーム対応研修
------------------------------------------------------------------------------
CS戦略、社員研修、サービス改善、カスハラ対策等はアックスラーニングへ
https://www.ax-learning.jp/